NISAのつみたて投資枠とは?
最初に、NISAのつみたて投資枠はどのような制度なのかを解説します。非課税期間や年間投資枠など、旧制度とは変わった点もいくつかあるので、順番にチェックしていきましょう。
旧制度のつみたてNISAを引き継ぐ少額非課税制度

出典元:Getty Images
2024年1月に開始したNISAのつみたて投資枠は、従来のつみたてNISAの後継である少額非課税制度です。株式や投資信託などの金融商品を購入し、売却時に得られる分配金や譲渡益が非課税になります。
制度の背景には長期・積立・分散投資を支援する目的があり、投資対象が一定の要件を満たす金融商品に限定される点は、つみたてNISAもつみたて投資枠も変わりません。投資初心者も取り組みやすく、節税しながら資産形成ができる制度として活用されています。
つみたて投資枠からの変更点として、従来の一般NISAを引き継ぐ成長投資枠との併用が可能です。さらに非課税保有期間が無期限化されたほか、年間投資枠や非課税保有限度額が増額されるなど、従来よりも長期投資に適した制度になりました。
※参考:金融庁「NISAを知る」(外部サイト)
成長投資枠とは年間投資枠などが異なる

出典元:Getty Images
つみたて投資枠と成長投資枠は、年間投資枠や投資対象商品などが異なります。
非課税期間は両方とも無期限ですが、年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。購入方法を見ると、つみたて投資枠は積立投資のみであるのに対し、成長投資枠は積立投資も一括投資も行えます。
また、つみたて投資枠で投資できるのは、長期の積立・分散投資に適していると金融庁が認めた投資信託のみです。一方の成長投資枠では、上場株式や投資信託などに投資できます。
両者の違いを比較すると、成長投資枠はより自由度の高い投資が可能です。2つの枠は併用できるため、自身の投資プランに合わせて枠を使い分けるとよいでしょう。
※参考:金融庁「NISAを知る」(外部サイト)
NISAのつみたて投資枠はデメリットしかない? 注意点は大きく5つ
まずは、つみたて投資枠のデメリットを解説します。実際につみたて投資枠を始めてから後悔しないように、あらかじめ確認しておきましょう。
元本割れして資産が減る可能性がある

出典元:Getty Images
つみたて投資枠で投資できる投資信託は、元本保証されていません。運用成績次第では資産が減ってしまう可能性があります。つみたて投資枠に限った話ではありませんが、投資は余剰資金で行うものです。生活に支障が生じない範囲で積立額を設定しましょう。
どうしても元本割れに耐えられない人は、つみたて投資枠ではなく1,000万円までなら銀行が倒産しても元本が保証される定期預金や、国が元本を保証する個人向け国債を検討してみてください。ただし、定期預金や個人向け国債では大きなリターンを期待できません。リスクが低い金融商品はリターンも低くなることを理解しておきましょう。
投資できる金融商品が限定的

出典元:Getty Images
つみたて投資枠で運用できる金融商品は、金融庁が選定した投資信託に限られます。個別企業の株式や不動産投資信託などは購入できません。投資先の選択肢が少ないので、さまざまな金融商品で資産運用したい人は、物足りなく感じられることもあるでしょう。
投資信託以外の金融商品にも興味がある場合は、つみたて投資枠ではなく成長投資枠がおすすめです。成長投資枠なら、株式をはじめとしたさまざまな種類の金融商品に投資できます。
新NISAでは2つの枠を併用できるため、成長投資枠では株式投資を行い、どちらの枠でも投資できる商品はつみたて投資枠で運用するなどの使い分けも可能です。
自分が買いたいタイミングで金融商品の購入ができない

出典元:Getty Images
つみたて投資枠は原則、定期的に一定額を購入する積立投資しか認められていません。自分が投資したいタイミングで金融商品を購入できないことを覚えておきましょう。証券会社によってはボーナス設定月を決めて追加投資できますが、毎月または毎日積立投資を行うことが前提です。
タイミングを見て一括投資をしたい人は、成長投資枠などほかの運用方法を検討しましょう。
損失が出た場合は節税メリットを得られない

出典元:Getty Images
つみたて投資枠では、損失が出たときに節税メリットを得られないことも理解しておく必要があります。利益が生じても税金がかからない代わりに、損失が出てもほかの課税口座との損益通算ができません。
損益通算とは、同一年内に生じた利益と損失を相殺できる仕組みのこと。例えば、同じ年に商品Aで20万円の損失、商品Bで20万円の利益があった場合は利益0円として税金を計算できます。
つみたて投資枠は損益通算ができないため、損失が出ていてもほかの課税口座で利益が出ていれば課税されます。損失を繰り越して、翌年以降の利益から控除できる繰越控除が使えない点にも注意が必要です。
つみたて投資枠では一時的に損失が出ても、長期運用によってトータルの収支がプラスに転じる可能性もあります。日々の値動きに一喜一憂せず、コツコツと積み立てを続けることが大切です。
非課税投資枠は120万円まで。成長投資枠より少ない

出典元:Getty Images
つみたて投資枠の非課税投資枠は年120万円です。成長投資枠の年240万円と比較すると2分の1にとどまります。つみたて投資枠では少額の長期運用が基本になるため、より大きな資金を運用したい場合は成長投資枠のほうが適しているでしょう。
また、非課税保有限度額は1,800万円に拡大されましたが、つみたて投資枠の年間投資枠だけで非課税保有限度額を使い切るのは難しいといえます。つみたて投資枠と成長投資枠は併用できるため、非課税保有限度額を有効活用するなら2つの枠の併用がおすすめです。
併用する場合、非課税保有限度額1,800万円のうち成長投資枠の分は1,200万円に制限されることを理解しておきましょう。
デメリットだけではない! NISAのつみたて投資枠のメリット
つみたて投資枠にはデメリットだけではなく、メリットもあります。ここからは、6つのメリットを紹介するので、つみたて投資枠の利用を検討している人は今すぐチェックしましょう。
運用益は非課税! 複利効果で利益を増やしやすい

出典元:Getty Images
通常、投資の運用益には20.315%の税金が発生しますが、つみたて投資枠では無期限で非課税になります。利益をそのまま再投資に回せるので、複利効果によって資産を効率よく増やせるでしょう。
複利効果とは、利益の再投資によって利益が利益を生み出す仕組みのこと。運用期間が長くなるほど、利益が雪だるま式に増えていきます。例えば、毎月1万円を利回り3%で20年間運用した場合、元本240万円に対する運用益は約88万円。最終的な資産は300万円を超えます。
ほかの積立金額や運用利回りのパターンが気になる人は、金融庁の公式サイト(外部サイト)でシミュレーションできるので一度試してみるとよいでしょう。
少額から始められる

出典元:Getty Images
金融機関によっては、つみたて投資枠で運用する投資信託を毎月100円から購入できることもあります。個別株を買う場合は10万円以上かかる場合も多いので、つみたて投資枠は気軽に始められる投資のひとつといえるでしょう。
つみたて投資枠の積立額は、あとからでも自由に変更できます。まずは無理のない範囲で始めて、慣れてきたころに積立額を増やしていくのもよいでしょう。
損失のリスクを軽減できる投資方法のため初心者も取り組みやすい

出典元:Getty Images
つみたて投資枠は低リスクの投資手法を実践できるため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。つみたて投資枠で実践できる投資手法は、ドルコスト平均法と呼ばれます。
ドルコスト平均法とは、同じ商品を毎月一定額購入し続ける手法のこと。価格が高いときは少なめに、価格が安いときは多めに購入できるので、平均購入金額を下げられます。
つみたて投資枠では、無期限の非課税期間を活かして資産運用できることもポイントです。長期投資によって、短期的な価格変動による損失のリスクを抑えられます。
購入手数料は無料! 低コストで運用できる

出典元:Getty Images
つみたて投資枠で購入できる投資信託は、購入手数料が無料です。信託報酬も低く抑えられているため、低コストで資産運用ができます。
信託報酬とは、資産運用を専門家に任せるための手数料のこと。投資信託を保有している限り支払い続けなければならないので、最終的な資産額に大きく影響します。
NISAは金融庁が運用コストの低い投資信託を厳選しているので、初心者でも効率的な資産運用が可能です。
自分で購入のタイミングを考える必要がない

出典元:Getty Images
つみたて投資枠では、購入頻度と積立金額を一度設定すれば、自動的に投資信託の買付が行われます。自分で価格の動向を細かくチェックしたり、購入するタイミングを考えたりする必要がないのは、大きなメリットといえるでしょう。
一括投資のほうが短期間で大きなリターンを狙えますが、取引のタイミングを正確に予測することはプロでも困難です。機械的に積立投資ができるつみたて投資枠であれば、価格変動による損失のリスクを抑えながら、着実に資産形成ができるでしょう。
お金の余裕がなくなったらいつでも引き出し可能

出典元:Getty Images
つみたて投資枠は、いつでも資産の引き出しが可能です。教育資金やマイホームの頭金など、まとまった資金が必要になった際には、保有する商品を売却して換金できます。iDeCoでは原則60歳まで資産を引き出せないので、つみたて投資枠の自由度は高いといえるでしょう。
お金に余裕がない場合は、すぐに積み立てを中止できるのもポイントです。ただし、つみたて投資枠は長期投資のための制度なので、短期間での売却や積み立ての中止はおすすめしません。売却時に価格が下がっていれば損をすることもあるので、換金するタイミングには特に注意しましょう。
NISAのつみたて投資枠が向いている人の特徴
次に、つみたて投資枠に向いている人の特徴を紹介します。自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
投資にまとまった資金を用意することができない人

出典元:Getty Images
まとまった資金を用意できない人は、つみたて投資枠に向いているといえます。ネット証券なら毎月100円で積立投資ができることもあるので、少額からでも気軽に始められるでしょう。
つみたて投資枠の目的は、一括投資で大きな利益を狙うことではありません。少額の積立投資を長期間にわたって継続することで、損失のリスクを抑えながら着実に利益を積み上げていくのが基本的な考え方です。
積立額はあとからでも変更できます。投資に慣れてきたころに、少しずつ積立金額を増やしていくのも選択肢のひとつです。
これから投資を始めたいと考えている人

出典元:Getty Images
投資経験のない初心者にも、つみたて投資枠での資産運用をおすすめします。つみたて投資枠で運用できるのは、金融庁が厳選した低コストの投資信託のみ。商品選定に必要な知識がなくても、比較的安全に資産運用ができるでしょう。
つみたて投資枠で投資経験を積み、資金にも余裕ができた場合は、つみたて投資枠の対象外となっている株式などにも投資してみるのがおすすめです。
忙しくて投資に時間をかけられない人

出典元:Getty Images
忙しくて投資の勉強や商品選びに時間がかけられない人は、つみたて投資枠を選びましょう。先述のとおり、つみたて投資枠では購入頻度や積立額をあらかじめ設定しておけば、自動的に積立投資を続けてくれます。取引のタイミングや投資先の選定に時間をかける必要はありません。
機械的に積立投資するので、感情に左右されることなく投資を続けられるのもメリットです。一時的な価格変動に惑わされて、商品を手放してしまう事態も避けられるでしょう。
NISAのつみたて投資枠で失敗しないためのポイント
最後に、つみたて投資枠で後悔しないための注意点を解説します。つみたて投資枠を始める前に、確認しておきましょう。
課税口座の資産をNISA口座に移管することはできない

出典元:Getty Images
特定口座や一般口座をはじめとした通常の課税口座から、NISA口座へ資産を移管することは認められません。つみたて投資枠を始める際は、ゼロから資産を積み立てる必要があります。
NISA口座で保有する投資信託を、ほかの課税口座へ移管することは可能です。ただし、これから価格下落が続きそうな投資信託を除いて、移管するメリットはほとんどありません。できるだけつみたて投資枠で運用し、利益を非課税で受取るほうが賢明といえるでしょう。
NISA口座は1人1つまで! 証券会社選びにこだわろう
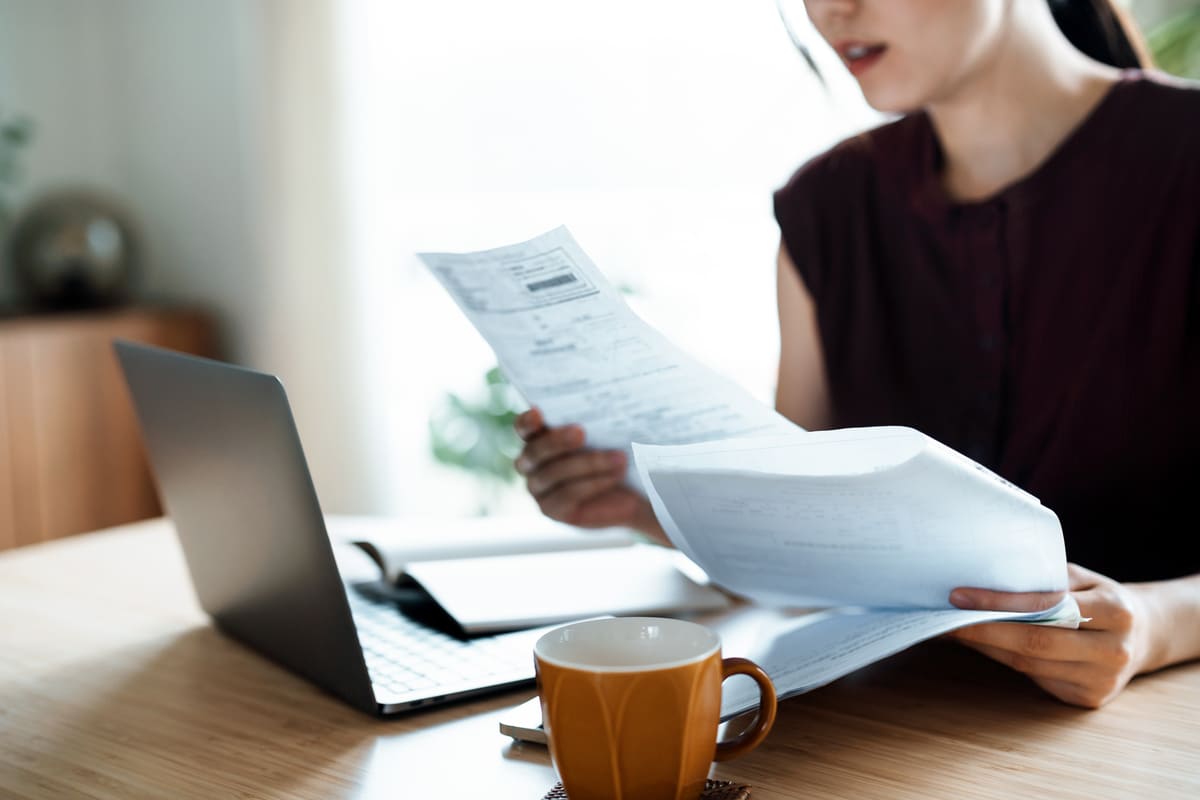
出典元:Getty Images
NISA口座は、1人1口座しか開設できません。証券会社によって取扱う銘柄や最低積立額が異なるので、口座の開設先は慎重に見極めましょう。
つみたて投資枠を始める際は、取扱銘柄数の多いネット証券がおすすめです。大手ネット証券では200種類近くの銘柄が用意されているので、投資の幅が広がります。
どの証券会社を選んでいいのか迷ったときは、以下のページをチェックしてみてください。各証券会社のサービス内容をランキング形式でまとめているので、口座の開設先を決める際に役立てられるはずです。

