iDeCoで所得控除を受けるには年末調整や確定申告が必要

出典元:Getty Images
iDeCoの掛金全額には小規模企業共済等掛金控除が適用され、所得税・住民税を節税できます。所得控除を受けるには、年末調整か確定申告が必要です。
会社員や公務員は年末調整または確定申告、自営業者は確定申告で控除を申請しましょう。会社員や公務員は原則、年末調整で手続きすれば確定申告は不要ですが、年末調整の時期に必要な書類をそろえられない場合などは確定申告が別途必要です。
iDeCoで年末調整するといくら戻ってくる? 還付金額の計算シミュレーション

出典元:Getty Images
年末調整・確定申告でどれくらいの税金が戻ってくるかは、課税所得の金額によって異なります。
所得税の計算式は「課税所得 × 所得税率 - 税額控除額」です。iDeCoを利用している場合、拠出した掛金と同じ額だけ課税所得が減るので、そのぶん払いすぎていた所得税が還付されます。
所得税率と税額控除額は課税所得に応じて変動するので、詳しくは国税庁の公式サイト(外部サイト)を確認してみてください。
例えば、年収400万円で毎月の掛金が1万円の場合、1年間で節税できる金額の目安は所得税6,000円、住民税12,000円です。所得控除による税控除額はiDeCo公式サイト(外部サイト)でシミュレーションできるので、自身の節税金額が気になる人は一度試してみるとよいでしょう。
年末調整と確定申告のどっちが必要? 申告が不要なケースとは?
iDeCoで所得控除を受けたいものの、年末調整と確定申告のどちらが必要なのかわからない人もいるでしょう。年末調整が必要なケース、確定申告が必要なケース、申告不要のケースをそれぞれ解説するので、自分がどれに該当するかチェックしてみてください。
個人払込を選択している会社員・公務員は年末調整が必須

出典元:Getty Images
会社員や公務員で、iDeCoの掛金を個人払込で支払っている人は年末調整が必要です。個人払込とは、個人の口座から掛金を拠出する方法を指します。
勤務先が従業員の税額計算を行うには、iDeCoの掛金などを含む所得控除の金額を把握しなければなりません。個人払込を選択している場合、勤務先はiDeCoの掛金額を把握できないため、年末調整で申告する必要があります。
自営業者や年末近くにiDeCoに加入した人などは確定申告を行う

出典元:Getty Images
自営業者や、年末近くにiDeCoに加入した会社員などが所得控除を受けるには、確定申告が必要です。
そもそも自営業者やフリーランスの人には年末調整がありません。iDeCoを含む各種控除を適用するには、確定申告で申請する必要があります。
会社員や公務員であっても、年末近くにiDeCoに加入して年末調整ができなかった場合は確定申告が必要です。年末調整ではiDeCoの払込実績を証明する書類が必要ですが、年末近くに加入すると書類の準備が間に合わない場合があります。
書類の到着が遅れて年末調整に間に合わなかった場合や、年末調整の手続き自体を忘れてしまっていた場合は、確定申告をして所得控除を受けましょう。
事業主払込を選択している会社員・公務員は申告が不要

出典元:Getty Images
会社員や公務員が掛金の納付を事業主払込にした場合、年末調整は不要です。事業主払込とは、iDeCoの掛金が給与天引きで支払われる仕組みのことで、所得控除の処理もすべて会社が代行してくれます。
年末調整の手続きをしたくない人は、事業主払込を利用するのがおすすめです。ただし、産休や育休などで給与が支払われない期間は、掛金の拠出がストップするので注意しましょう。
iDeCoの年末調整の書き方を3ステップで解説
はじめてiDeCoの年末調整をする人は、何をどこに書くのか、証明書のどの部分を添付すればよいのかなどがわからないかもしれません。ここでは、iDeCoの年末調整の書き方を詳しく解説します。
手順1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受取って保管する

出典元:Getty Images
まずは、国民年金基金連合会から届く小規模企業共済等掛金払込証明書を受取り、大切に保管してください。
小規模企業共済等掛金払込証明書は、1年間のiDeCoの掛金額を証明する書類です。加入している金融機関によりますが、9月までに掛金の引き落としがある人なら10月下旬には郵送されるでしょう。
11月以降に掛金の引き落としがある人は、証明書の発送が年末調整に間に合わず、確定申告の手続きが必要になる可能性もあります。
手順2:「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入する

出典元:Getty Images
年末調整の時期になったら「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先から受取り、必要事項を記入します。
記入が必要な項目は、申告書の右下の小規模企業共済等掛金控除にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄です。小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されている金額を記入してください。
手順3:書類を勤務先へ提出する

出典元:Getty Images
保険料控除申告書の記入が完了したら、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して勤務先に提出しましょう。払込証明書の貼り方は、左上に重要と記載があるページを切り取って添付します。
会社によって年末調整の期限は異なるため、小規模企業共済等掛金払込証明書の受取りが遅れそうな場合は、年末調整に間に合うかどうかをあらかじめ担当者に確認しておきましょう。
年末調整の手続きをする時点までに書類の受取りが間に合わなかった場合は、期限までに確定申告を行う必要があります。確定申告の手続きは後述するので、あわせてチェックしてみてください。
iDeCoの確定申告のやり方も知っておこう
個人事業主をはじめとした自営業者や、年末調整ができない会社員・公務員は確定申告が必要です。年末調整と比べて手続きが煩雑になるため、手順をしっかり確認しましょう。
手順1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受取って保管する

出典元:Getty Images
まずは、国民年金基金連合会から届く小規模企業共済等掛金払込証明書を受取り、確定申告の時期まで大切に保管してください。
小規模企業共済等掛金払込証明書は、1年間のiDeCoの掛金額を証明する書類です。加入している金融機関にもよりますが、遅くとも1月下旬には届きます。確定申告の受付期間は2月16日〜3月15日なので、証明書を紛失しない限り手続きが間に合わないことはないでしょう。
手順2:「確定申告書」に必要事項を記入する
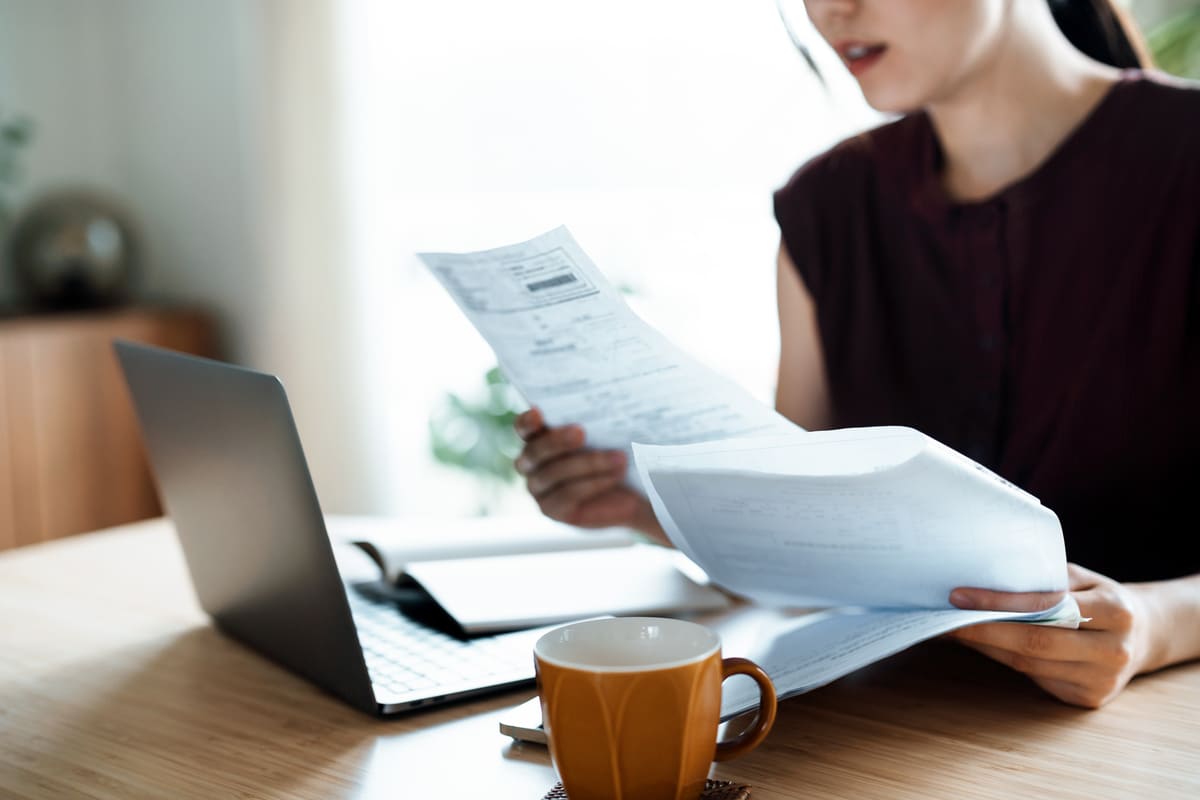
出典元:Getty Images
確定申告の時期になったら、税務署の窓口などから確定申告書を入手して必要事項を記入しましょう。国税庁の公式サイト(外部サイト)を利用すれば、スマホやパソコンからでも確定申告書の作成が可能です。
iDeCoの控除を受けるには、確定申告書の第一表と第二表に記入する必要があります。まずは、小規模企業共済等掛金払込証明書に記載された合計金額を確認し、第一表にある小規模企業共済等掛金控除の欄に記入しましょう。
続いて、第二表にある小規模企業共済等掛金控除の欄のうち、「保険料等の種類」に「個人型確定拠出年金」と記入します。「支払保険料等の計」と「うち年末調整等以外」には、小規模企業共済等掛金払込証明書に記載された合計金額を記入してください。
ちなみに、勤務先で年末調整をした会社員・公務員が医療費控除などのために確定申告する場合は、第二表の書き方が異なります。「保険料等の種類」には「源泉徴収分」と書き、「支払保険料等の計」には源泉徴収票の「社会保険料等の金額」上段の内書きを記入しましょう。
手順3:書類を税務署へ提出する

出典元:Getty Images
確定申告書に小規模企業共済等掛金払込証明書を添付し、税務署に提出すれば手続き完了です。以前は源泉徴収票も提出する必要がありましたが、2019年4月1日以降は添付が不要となりました。
電子申告システムのe-Taxを使えば、確定申告書の電子データをオンライン上で提出でき、小規模企業共済等掛金払込証明書の添付も不要です。税務署に足を運ぶ時間がない人はぜひ活用してください。
確定申告の期限は原則2月16日から3月15日と決められています。期限内に確定申告書の作成や提出などを済ませる必要があるので、早めに準備を始めましょう。
iDeCoの年末調整をスムーズに終わらせるためのポイント
iDeCoの年末調整を滞りなく済ませたいのであれば、必要な書類を保管し、年末調整のやり方を確認しておくことが大切です。iDeCoの年末調整を円滑に進めるポイントを解説するので、チェックしておきましょう。
年末調整に必要な書類をなくさない

出典元:Getty Images
iDeCoの年末調整をスムーズに終わらせたいなら、必要な書類を紛失しないように心がけましょう。国民年金基金連合会から送付される小規模企業共済等掛金払込証明書は、年末調整の際に原本を提出する必要があります。
小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合は、再発行が必要です。小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書をiDeCo口座のある金融機関に提出すれば、2週間程度で発送されます。
しかし、紛失に気づいたタイミング次第では、再発行が年末調整に間に合わない可能性もあるでしょう。小規模企業共済等掛金払込証明書は毎年10月頃に送付されるので、手続きが始まるまで大切に保管することが大切です。
払込証明書の電子データはマイナポータルでダウンロードできる

出典元:Getty Images
勤務先が対応していれば、小規模企業共済等掛金払込証明書の電子データをマイナポータルでダウンロードするのもおすすめです。証明書原本の管理・保管の手間がかからず、iDeCoの年末調整の申告手続きも簡単になります。
電子証明書として使える電子データをダウンロードするには、事前準備が必要です。マイナポータルの利用者登録と、iDeCoオンライン手続きサービスの利用申込みを済ませておきましょう。
電子データがあれば、小規模企業共済等掛金払込証明書の原本を紛失した場合に対処しやすい点もメリットです。電子データはマイナポータルからダウンロードできるので、紛失しても再発行を依頼する必要がありません。
勤務先ごとの年末調整のやり方を確認しておく

出典元:Getty Images
年末調整をスムーズに行うために、勤務先の年末調整のやり方もチェックしておきましょう。年末調整の手続き方法や期限は勤務先によってさまざまです。
企業によっては「給与所得者の保険料控除申告書」を使用せず、専用の人事システムに入力して年末調整を行うこともあります。また、年末調整の期限は11月中旬〜下旬が一般的ですが、勤務先によっては時期が異なっていたり、申告期間が短かったりすることも。
年末調整は慣れない作業で時間がかかる可能性があるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。気づいたら申告期間を過ぎていたなどの失敗をしないためにも、勤務先の案内をきちんと確認しておきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の年末調整に関するQ&A
最後に、iDeCoの年末調整に関するよくある質問を紹介します。iDeCoの加入を検討している人や、加入後にはじめて年末調整を行う人はぜひチェックしてみてください。
小規模企業共済等掛金払込証明書のハガキはいつ届く?

出典元:Getty Images
小規模企業共済等掛金払込証明書の発送予定日は、掛金が引き落とされた時期によって異なります。
9月までに掛金の引き落としがある場合は、10月下旬頃には手元に届くでしょう。初回引き落としが10月なら発送は11月下旬、11月なら発送は12月下旬、12月なら翌年1月下旬と、引き落とし時期が遅くなるにつれて発送時期も後ろ倒しになります。
小規模企業共済等掛金払込証明書が届かず、年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。iDeCoは口座開設にも1〜2カ月を要するので、確定申告を避けたい人は加入するタイミングに十分注意しましょう。
年末調整と確定申告の両方をし忘れた場合はどうする?

出典元:Getty Images
年末調整と確定申告のどちらも忘れた場合は、還付申告をしましょう。税金の還付を受ける還付申告をすれば、申告を忘れて多く納めすぎた所得税などが戻ってきます。
iDeCoの掛金を拠出した年の翌年の1月1日から5年以内であれば、還付申告が可能です。例えば、2024年にiDeCoで掛金を拠出した分は、2025年1月1日〜2029年12月31日に申告できます。
還付申告の手続き方法は確定申告と変わりません。確定申告と同様に、国税庁の確定申告書等作成コーナー(外部サイト)で書類を作成できます。
iDeCoで年末調整すると、税金はいつ戻る?

出典元:Getty Images
年末調整の完了時期によっても異なりますが、所得税は早ければ年内、遅くても翌年の1月下旬には還付されます。
確定申告の場合、混雑状況によっては最大で1カ月半程度かかる場合もあるので注意してください。確定申告で還付を早めに受けたい人は、2〜3週間で還付金が振込まれるe-Taxを活用しましょう。
所得税とは異なり、年末調整・確定申告を行っても住民税は還付されません。所得控除を申告した分は、翌年6月以降の住民税に反映されます。
iDeCo開設先を比較するなら証券会社ランキングをチェック
iDeCo口座を開設して資産運用をしているものの、運営管理手数料が高い、取扱商品が少ないなどの不満がある場合は、iDeCo口座の金融機関変更を検討してみましょう。
以下のページでは、iDeCo口座で手数料が安い証券会社のランキングを紹介しています。iDeCoにおすすめの証券会社の選び方も解説しているので、変更先を検討する際の参考にしてみてください。

