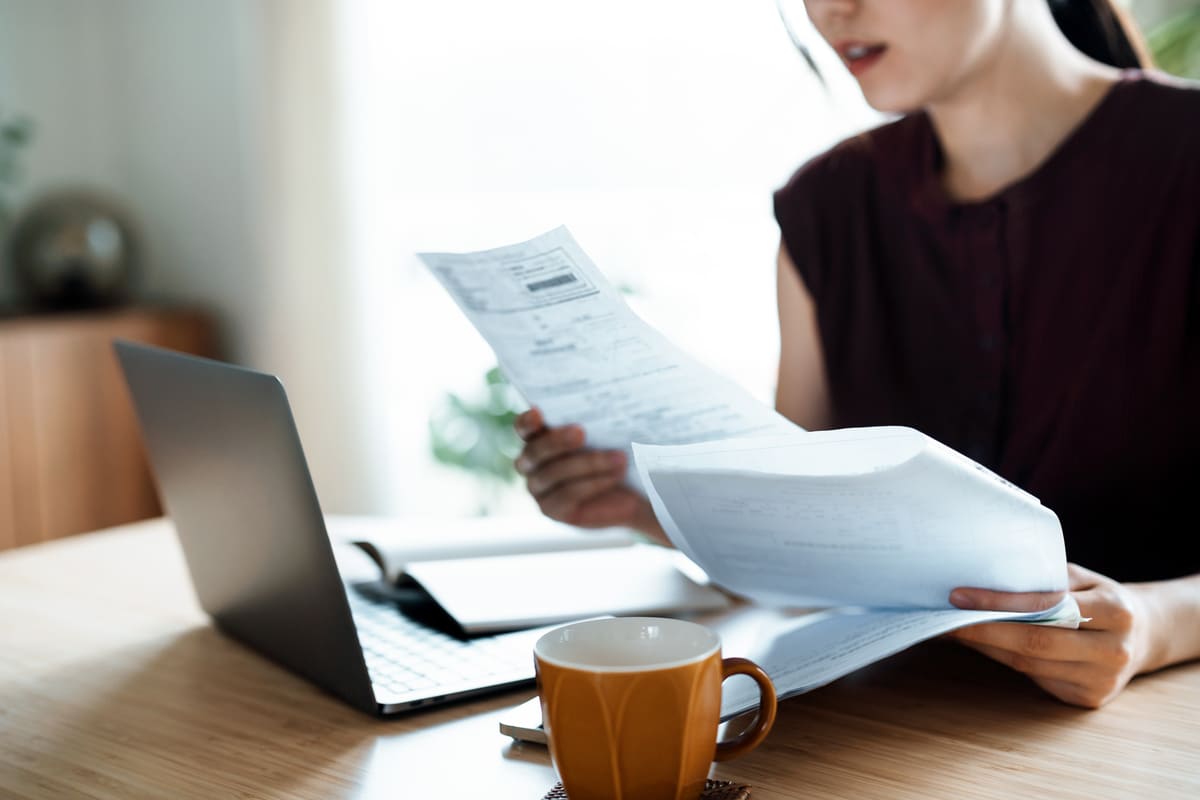NISA(一般NISA)とつみたてNISAとは?
NISA(一般NISA)とつみたてNISAは、2023年に終了した旧NISAの種類のことです。そもそもNISAとは、一定の投資額以内で得られた利益を非課税で受取れる制度を指します。
2024年からは新NISAが始まり、NISA(一般NISA)とつみたてNISAも新制度へ移行しました。ここでは旧NISA・新NISAの概要をそれぞれ解説します。
一般NISAとつみたてNISAは2023年終了の旧NISA制度

出典元:Getty Images
NISA(一般NISA)とつみたてNISAは旧NISA制度の種類であり、どちらも2023年に終了しています。そもそもNISAは個人の資産運用をサポートするための制度としてスタートしたもので、一定の投資額以内で得られた利益を非課税で受取れる点が特徴です。
通常の投資では、利益に対して20.315%の税金が発生します。例えば、100万円の利益が出ても約20万円は税金として差し引かれるので、手元に残るのは80万円のみ。しかし、NISAを利用すれば、100万円をそのまま受取れます。
旧NISAは大きく分けて、一般NISAとつみたてNISAの2種類です。一般NISAは、年間120万円までの投資で得られた利益が最大5年間非課税になる制度のこと。一方のつみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円、非課税期間は最大20年間です。
2024年から開始された新NISA制度では、成長投資枠が一般NISAの役割を、つみたて投資枠がつみたてNISAの役割を引き継いでいます。なお、制度終了後も非課税期間を迎えるまでは一般NISAとつみたてNISAの運用を継続できますが、新たな投資はできません。
旧NISAは新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠に引き継がれる

出典元:Getty Images
2024年1月からは新しいNISA制度が開始されました。新NISAには、一般NISAを引き継ぐ成長投資枠と、つみたてNISAを引き継ぐつみたて投資枠が設けられています。
成長投資枠は年間240万円まで非課税で投資でき、投資信託や株式、ETFなどを運用可能です。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円で、金融庁の基準を満たした一定の投資信託に投資できます。
新NISAでは2つの枠を併用できるうえ、非課税期間の無期限化や非課税投資枠の拡充など、制度が大幅に変更されました。旧NISAとの具体的な違いは後述するので、参考にしてみてください。
旧NISAと新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠の違いを比較
新NISAは旧NISAを引き継いだ制度ですが、非課税期間や非課税投資枠などに違いがあります。ここからは、新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠と旧NISAの違いを比較してみましょう。
非課税期間|旧NISAは期限つき、新NISAは無期限

出典元:Getty Images
投資で得た利益が非課税になる期間を比較すると、旧NISAは期限が決まっていますが、新NISAは期限がありません。旧NISAの非課税期間は一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間です。一方、新NISAは成長投資枠・つみたて投資枠ともに非課税期間が無期限化されています。
無期限化されたことによって運用中に非課税期間を考慮する必要がなくなり、より長期的な目線での資産運用がしやすくなりました。また、何年運用しても運用益に税金がかからないため、資産をより増やしやすくなったといえます。
非課税投資枠|旧NISAに対して成長投資枠は2倍、つみたて投資枠は3倍

出典元:Getty Images
新NISAでは、年間の非課税投資枠が旧NISAに比べて大きく拡大されました。一般NISAの非課税投資枠は年間120万円でしたが、成長投資枠では年間240万円です。また、つみたてNISAの非課税投資枠が年間40万円であるのに対し、つみたて投資枠では年間120万円まで投資できます。
なお、旧NISAでは一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選択する必要がありましたが、新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能です。2つの枠を併用すると、年間360万円まで非課税で投資できます。
非課税保有限度額|新NISAは2つの枠の合計が1,800万円。再利用も可能

出典元:Getty Images
旧NISAからの変更点として、新NISAでは非課税保有限度額が拡大されました。成長投資枠とつみたて投資枠をあわせた上限は1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円まで利用できます。
旧NISAの非課税保有限度額を見ると、つみたてNISAは800万円(年間投資枠40万円×非課税期間20年間)、一般NISAは600万円(年間投資枠120万円×非課税期間5年間)です。新NISAでは2つの枠をあわせて1,800万円まで保有できるため、非課税保有限度額は大幅に有利になったといえます。
加えて、非課税保有限度額を再利用できる点も新NISAの特徴です。保有中の商品を売却すると、売却した商品の取得金額相当分が翌年以降に復活して再利用できます。
例えば、非課税保有限度額を1,800万円まで利用している場合に、取得金額100万円の商品を売却すると非課税保有限度額が1,700万円に変わり、翌年以降に100万円分の再投資が可能です。
投資対象|新旧でほぼ変更なし。成長投資枠(一般NISA)は対象が幅広い

出典元:Getty Images
新NISAの投資対象は旧NISAからほとんど変更がありません。つみたてNISAを引き継ぐつみたて投資枠の投資対象は、金融庁が選定した一部の投資信託のみです。一般NISAを引き継ぐ成長投資枠は、投資信託や日本株式、米国株式、新規公開株式など幅広い投資対象から選べます。
ただし、一般NISAと成長投資枠は対象商品が一部異なり、成長投資枠では整理・監理銘柄の上場株式を購入できません。一般NISAでは投資できた信託期間20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託なども、成長投資枠では対象外です。
投資方法|新旧同じ。つみたて投資枠(つみたてNISA)は積立のみ

出典元:Getty Images
選択できる投資方法は新NISAも旧NISAも同じです。つみたて投資枠(つみたてNISA)は積立投資のみ、成長投資枠(一般NISA)は一括投資と積立投資の両方を選べます。
一括投資は、タイミングを見てまとまった資金を一度に投資する方法です。底値で買えれば積立投資より大きなリターンを期待できますが、適切な購入のタイミングを判断するのはプロでも難しいといわれています。
積立投資は、毎月決まった金額を投資し続ける方法です。価格が高いときは少ない数量、安いときは多い数量を購入することで、平均購入金額を抑えられます。
自由度が高いのは成長投資枠(一般NISA)ですが、初心者がいきなり一括投資をすると失敗する可能性もあるでしょう。リスクをふまえたうえで、自分の知識・経験に応じた方法を選択することが大切です。
新NISAを始めるなら成長投資枠とつみたて投資枠のどちらがおすすめ?
新NISAを始めようと思っているものの、成長投資枠とつみたて投資枠のどちらを利用したらよいか迷っている人もいるのではないでしょうか。ここからは、タイプ別にどちらがおすすめかを解説します。
株式投資がしたい人、まとまった資金がある人は成長投資枠

出典元:Getty Images
株式投資がしたい人やまとまった資金がある人は成長投資枠の利用を検討しましょう。
まず、成長投資枠なら一括投資が可能です。取引のタイミング次第で、短期間でも大きな利益を狙えます。積立投資しかできないつみたて投資枠では、コツコツと利益を積み上げていくのが基本です。
成長投資枠であれば、株式をはじめとしたさまざまな金融商品にも投資できます。つみたて投資枠では、投資対象が投資信託に限定されるので、投資経験者にとっては物足りなく感じられることもあるでしょう。
また、成長投資枠の非課税投資枠は年間240万円と、つみたて投資枠の2倍です。十分な資金がある人は、成長投資枠で運用したほうが非課税メリットも大きくなることを覚えておきましょう。
投資初心者の人、長期で積立投資したい人はつみたて投資枠

出典元:Getty Images
投資初心者や長期で資産運用したい人は、つみたて投資枠を選びましょう。
つみたて投資枠は、金融庁が厳選した投資信託に投資対象が限定されています。購入手数料が無料、保有コストが安いなどの条件を満たした優良銘柄だけが選ばれているため、投資の知識がない初心者でも商品選定に迷わずに済むでしょう。
毎月決められた金額を投資する積立投資で運用するので、自分で投資するタイミングを考える必要がないのもメリットのひとつ。手間がかからないのに加え、投資対象は長期の資産運用に適した商品に限定されているため、長期でコツコツ投資したい人にもつみたて投資枠がおすすめです。
旧NISAと新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)に関するQ&A
旧NISAと新NISAに関するよくある質問をまとめました。口座を開設する前にチェックしましょう。
成長投資枠(一般NISA)とつみたて投資枠(つみたてNISA)は併用可能?

出典元:Getty Images
一般NISAとつみたてNISAは併用ができませんでしたが、成長投資枠とつみたて投資枠は併用が可能です。
旧NISAでは一般NISAからつみたてNISA、つみたてNISAから一般NISAへの変更は可能でしたが、どちらか一方を選択する必要がありました。一方、新NISAは成長投資枠とつみたて投資枠を併用でき、柔軟に使い分けることが可能です。
例えば、2つの枠を併用して大きな金額の投信積立をするのも選択肢のひとつ。つみたて投資枠で毎月積み立てられる上限は10万円ですが、成長投資枠を併用すれば毎月20万円分を上乗せできるため、非課税で毎月30万円の積立が可能です。
または、つみたて投資枠で投信積立をしながら、成長投資枠で株主優待のある企業の株式を購入したり、相場に応じて一括投資をしたりしてもよいでしょう。
ちなみに、成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。NISA口座は1人1つまでと決まっており、1つのNISA口座内で2つの枠を利用する仕組みです。複数の金融機関を利用できるわけではないため、NISA口座の開設先は慎重に選びましょう。
iDeCoとの違いは? 併用して加入できる?

出典元:Getty Images
新NISAは旧NISAと同様に、iDeCoとの併用が可能です。併用することにより、iDeCoとNISAの双方で非課税メリットが受けられます。
iDeCoは私的年金制度のひとつです。投資により得られた利益が非課税になる点は新NISAや旧NISAと同じですが、掛金が全額所得控除になる点が異なります。
所得控除によって所得税や住民税を節税できるので、新NISAや旧NISAよりもお得な制度といえるでしょう。ただし、iDeCoで積み立てた資産は原則60歳まで引き出せない点や、運用中は一定の手数料が毎月発生する点には十分注意してください。
旧NISAから新NISAに切り替える場合、必要な手続きは?

出典元:Getty Images
旧NISAから新NISAへ切り替える際に手続きは必要ありません。旧NISAのNISA口座を保有していた場合、同じ金融機関で自動的に新NISAの口座が開設されます。
旧NISAの積立設定も基本的に新NISAに引き継がれる仕組みです。一般NISAの積立設定は成長投資枠に、つみたてNISAの積立設定はつみたて投資枠の口座に自動で反映されます。ただし、一般NISAで投資していた商品のうち、成長投資枠から除外された銘柄は積立設定が引き継がれないので注意しましょう。
なお、旧NISAで保有していた商品を新NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。旧NISAと新NISAは別枠で扱われ、2024年以降も同時に運用することは可能です。ただし、旧NISAでの運用商品を新NISAでも運用したい場合は、一度売却し新NISA口座で再度購入する必要があると覚えておきましょう。
新NISA口座を開設するなら? おすすめ証券会社をチェック
新NISA口座を開設しようと思っているものの、どの証券会社にするか迷っている人もいるでしょう。以下のページでは、各証券会社のサービス内容をランキング形式でまとめています。新NISA口座の金融機関を選ぶ際の参考にしてみてください。